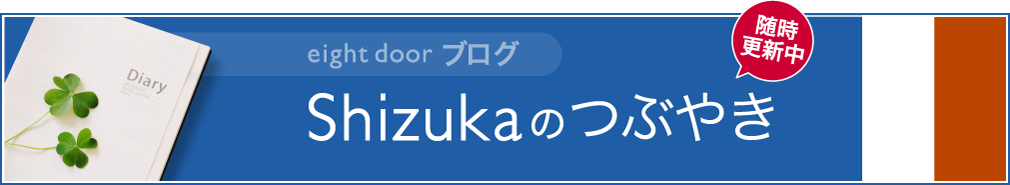10/30付デーリー東北紙「私見創見」にコラム掲載されました!
2018年10月30日
10月30日(火)付けデーリー東北紙の「私見創見」にコラムが掲載されました。
今回のテーマは、「人事評価への向き合い方」です。
向き合い方を変えると、人事評価制度の使い方、活かし方が変わってくると思うのです。
自分を高める道具、自分を見つめ直す道具として使ってみる価値はあるかもしれませんね。
詳しくは、写真をクリック!

【お知らせ】神戸で公開講座「人事評価者研修」を開催します♫
2018年10月24日
エイトドア主催第2弾の公開講座は、神戸で開催いたします。
テーマは、「医療従事者のための”わかりやすい”人事評価者研修」です。
日時:平成31年2月19日(火)10:00〜16:00(休憩1時間含む)
会場:兵庫県民会館1001号室
神戸市中央区下山手通4-16-3
参加費:6,000円(税込み、テキスト代を含みます)
お申込は、こちらから(^^)
☑ 弊社ホームページのお問い合わせから www.8-door.jp
☑ メールアドレス info@8-door.jp
☑ こくちーず(公開講座申し込みサイト)https://www.kokuchpro.com/event/kobe20190219/

平成29年度より地方公務員法改正により、人事評価制度を導入し、その結果を処遇に反映することが
義務化されました。
ということは、民間病院でもその取り組みは必要であるという捉えた方がいいということです。
それでも、人事評価制度を導入するとなると、職員の皆さんの反発、抵抗はあって当たり前のこと。
その反発、抵抗を少しでも軽減するために必要なのは、評価者教育なのです。
「評価する人は、きちんと評価するためのスキルをもっているの?」
「評価する人は、自分の基準で評価をしているんじゃないの?」
といったような被評価者の疑問や懸念を取り除くことが、人事評価制度定着の第一歩でもあります。
しかし、評価者教育はなかなか自院でするのは難しいものです。
外部講師にお願いしよう!にも、講師は誰にすればいいのか、研修費用が限られている、受講者の人数が少なすぎる・・
という問題を抱えていて、結局評価者教育ができていない!ということにお応えする公開講座です。
丸1日、どっぷり評価者研修ですが、わかりやすいことばで、解説いたします。
また、現場の事例を取り上げながら、人事評価を体験していただきます。
テキストは約50ページにもわたる充実感です。
是非、皆様のご参加をお待ちしております!
因みに、丁寧な講義と対応をしたいので、誠に勝手ながら30名様限定の講座とさせていただきますこと
ご了承下さいませ。
皆様のご参加、お待ちしております♪
面接で口数がすくないスタッフの対応(人事評価シリーズ19)
2018年10月15日
評価面接で口数が少ないスタッフの対応に困っている評価者も少なくありません。
何を言っても、「はい」しか言わない、こちらが話しかけると応えるが、それ以上のことは言わない等・・・
そこで、口数の少ないスタッフの特徴と対応を参考にしてみてはいかがでしょうか。

*~*~*~*~*~*
【特徴①】指示されたことだけ仕事をしているので受け身状態である。
⇒ いつも受け身で仕事をしているので、自分から話すことはない。
⇒ 指示されたら動くため、自分の意見を持っていない。
【対応例】指示した仕事について、伝えるべきことをしっかり伝える。
☆ 指示した仕事が確実に出来ている場合は、しっかりとほめる。
☆ 指示した仕事で自分自身が困ったことを聞く。
☆ 工夫した方がよいこと等スタッフを考えさせるようなことを尋ねると、
自分の意見を持っていないので余計に口数が少なくなる可能性があるので注意。
【特徴②】何を言っても無駄という気持ちがある。
⇒ 意見を言ったところで、どうせ受け入れられない。
⇒ 何を言っても、変わらないのだから、話しても無駄だと思っている。
⇒ 黙っている方が楽だと思っている。
【対応例】口数が少なくとも、スタッフが話した内容を丁寧に聞き分けて答える。
☆ 口数が少ないながらも、話したことはしっかりと聞く。
☆ 聞いたことを理解したという態度をとる(スタッフが話したことを繰り返して言うなど) 。
☆ 改善の意見と文句や批判を聞きわける。
改善や提案、工夫の意見の場合は、「そういう考えはいい考えだね」など同調して、意見を認める態度をとる。
【特徴③】上司、組織に対して批判的な気持ちがある。
⇒ 上司の考え、やり方、経営方針や方向性に賛同できない
⇒ 組織が何をやりたいのか理解できていない
【対応例】スタッフが何を考えているのか、まずは知ることから始める。
☆ 評価者の考えを押し付けず、まずはスタッフの考えを真摯に聞く。
☆ 日頃から組織の経営状況や方針・方向性を伝える機会を作る。
(会議で決定したこと、未決定でも課題がどのような方向に進んでいるのかを話す)
*~*~*~*~*~*
面接で口数が少ないからといって、無理矢理話をさせようと思っても、相手の気持ちが動かなければ、
その効果はありません。
面接の目的は、評価者が必ず伝えたいこと、スタッフから最低限訊いておきたいこと聞くでいいのです。
ことば少なくとも、面接の目的が達成されればいいのだと思って対応すると、
評価者の気持ちの負担が少なくなりませんか?
自己評価が低い人の対応(人事評価シリーズ18)
2018年10月09日
人事評価シリーズ17では、自己評価の高いスタッフへの対応について述べました。
シリーズ18では、反対に「自己評価が低いスタッフ」への対応です。
自己評価が高いスタッフの対応も、それはそれで難しいのですが、低すぎるのも問題です。
何故かというと、低すぎるということは、「自分はできていない」という自覚が常にあるからです。
医療の現場において、「できていない」という自覚をもって仕事をすることは、大変危険な状態で
仕事をしていることになると思いませんか。
そもそも、自己評価が低すぎるスタッフは、本当に「できていない」のでしょうか。

*~*~*~*~*~*
では、自己評価が低いスタッフには次のような対応をしてみましょう。
【特徴①】 とにかく自分に自信がない
⇒ 仕事を間違えたりすることはないけれど、何となく自信がない
⇒ いつも仕事が不確かで、ミスを犯すのではないかと不安でいっぱい
【対応例】 自信がないことと、仕事ができていないことは意味が違うことを伝える必要があるでしょう。
☆ 出来ている仕事は、こまめに現場でしっかりほめる。
☆ どんなところがきちんと出来ているのかを伝える。
☆ 反対に出来ていない仕事もしっかり伝え、出来ることと出来ないことのメリハリをつける。
【特徴②】 謙遜している
⇒ 仕事はできているが、できるという自己評価をすることに気が引ける
⇒ 自分よりできている人がいるのに、評価を高くすることはできない
⇒ 完璧はありえないのだから、評価が高くなることはありえないと思っている
【対応例】 謙遜することは悪いことではないが、正しく自分を評価し、自分が何ができる人かを伝えることは、
どのような仕事を任せられるかにつながるということを認識させる必要があります。
☆ 自己評価は、自分の仕事の事実を伝える場であることを理解させる。
☆ 出来ることとできないことをはっきりさせる。
☆ 自己評価は、今後の業務分担やキャリア開発に関連することを理解させる。
*~*~*~*~*~*
自己評価が高すぎても、低すぎても、自分自身を正しく認識しているとは言えません。
自己評価は自分だけのことではなく、仕事をする上で、周囲の人たちと何が協力できて、
何を協力してほしいのかの意思表示にもなるのです。
そう考えると、「正当に自分を評価する」力=「自己評価力」を身に着けること、大切なことだと思いませんか?
八戸の朝市、活気が最高です!
2018年10月07日
八戸の見どころ、今朝は「八戸館鼻岸壁の朝市」に行ってきました。
300軒以上のお店が連ねます。毎週日曜日に開催していて、夜が明けそうな時間から、
続々と各お店が開店します。
今は、全国各地から足を運んでくれるようで、駐車場は、全国各地のナンバーの車でいっぱいです。
新鮮な魚が驚くほどの安価で、新鮮な採れたて野菜もかごに大盛で、そして、焼きたてのパン、チヂミ、
ビーフシチューや煮込みハンバーグ、ここでしか食べられないくじら汁や八戸せんべい汁など、
ありとあらゆる食材が売られています。
*~*~*~*~*~*
あまりの安さと、代金をお店の方に渡すと、商品の入った袋に、ちょこっとおまけを入れてくれたりします。
今日は、青唐辛子(こちらでは「なんばん」の名前で売られています)を3かご買ったところ、
一握りの青唐辛子を足してくれました。
こういうことがあると、また行きたくなりますね。

是非、八戸にお越しの際は、朝市の活気ある雰囲気を味わっていただきたいなと思います。
300軒の立ち並ぶお店を何往復もしたくなること間違いないです♪
そして、買いすぎ注意!です!(^^)!
介護施設のためのキャリアパス制度運用点検講座、開催報告
2018年10月06日
10月5日(金)、八戸市総合福祉会館「はちふくプラザねじょう」にて、
介護施設のためのキャリアパス制度運用点検講座を開催いたしました。
弊社の初めての企画と開催で、県内の社会福祉法人2法人の皆様が参加してくださいました。
こじんまりですが、参加してくださったそれぞれの法人の制度について、
丁寧にアドバイスできたと思います。
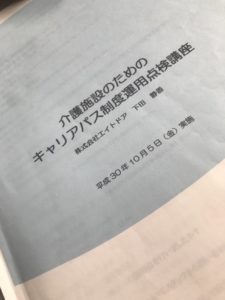
大変喜んでお帰りいただきました。
初めての公開講座にもかかわらず、お申込み、ご参加くださったことに
心より感謝申し上げます。
*~*~*~*~*~*
キャリアパス制度は、介護職員の処遇改善交付金の申請に必要ではありますが、
本来の目的を理解した上で、運用していただきたい制度です。
一人ひとりの職員のスキルを上げること、上がることでいい仕事、いいサービスが提供できること、
それによって利用者さんが喜び、家族が安心すること、施設が必要とされること、
結果として、施設運営が円滑に進み、それが職員に喜びや賃金で還元されること、
この循環を作ること
この考えを浸透させていきたいと思っております。
公開講座は、これからも定期的に開催いたします。
皆様のご参加、お待ちしております。