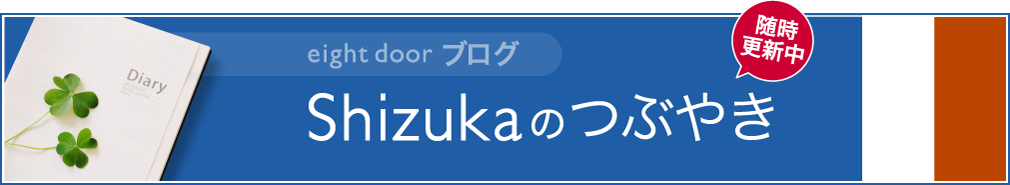自己評価が高い人の対応 (人事評価シリーズ17)
2018年09月26日
人事評価制度において、自己評価は、尊重するのが原則です。
が・・・、そうは言っても、上司評価と比較して、高いすぎるもしくは低いことは起こりえます。
そこで、自己評価が高い場合と低い場合の傾向とその対応について述べたいと思います。
シリーズ17では、高いスタッフの特徴と対応策についてです。
*~*~*~*~*~*
【特徴①】自己の能力を認めてほしいという気持ちがある
⇒ 「これだけ頑張っているのに自分を見てくれていない!」
⇒ 「自分は他のスタッフよりも知識や技術があるし、仕事も出来るのに!」
⇒ 「ちゃんとやっているんだから、もっと認めてほしい!」
【対応例】認めてほしいことが何かを聞くこと、本人が認めてほしいこととこちらが認めることの差違を埋めることが必要です。
☆ 上司評価の高い結果のフィードバックに時間をかける。
☆ 評価期間中に出した成果など、スタッフからとことん話しをさせる。(何を認めてほしいのかがわかるかも)
☆ 全体的に優れている能力をほめる。(例:「○○さんは、わかりやすく伝える力(伝達力)がありますよね」など)
☆ 上司評価が低く、自己評価が高い点については、特に具体的な事実だけをフィードバックする。
(「○○さんは、いつも××だよね」など絶対言わないこと!)

*~*~*~*~*~*
【特徴②】上司や周囲に威圧感を与えたいという気持ちがある
⇒ 「私は部署内で一番できるんだから評価が高いのは当たり前!」
⇒ 「上司は自分がこれだけできる人だってことを知らないんだな!」
⇒ 「自分はできるんだから、もっとやりがいのある仕事を担当させてほしいのに!」
⇒ 「私の方が上司よりも仕事ができるのを知らないんだな!」
⇒ 「どうせ上司評価が優先されるんだから、高くしておけば、下げにくいだろう!」
【対応例】上司に対して、自己評価を使って何を強調したいのかを聞き出すことが必要です。
☆ 【特徴①】の対応例
☆ スタッフの仕事上の不満を引き出し、それを訊く。
☆ やってみたい仕事を訊く。
☆ 責任のある仕事を任せてみる。
*~*~*~*~*~*
【特徴③】そもそも、評価基準がズレている
⇒ 「ちゃんとできたんだから、A評価でいいんでしょ?」(5段階評価の場合、標準にできているとB評価が一般的)
⇒ 「目標が達成できたんだから、S評価じゃないの?」
【対応例】面接で具体的な事例を使って、評価基準のズレを埋め合わせることが必要です。
☆ 基準をどこに置いているのか、スタッフから話をさせる。
☆ どのような経緯で、自己評価の結果になったのか、話をさせる。
☆ 上記の内容に応じて、基準のずれを正す。
*~*~*~*~*~*
【特徴④】自己評価を適当に行っている
⇒ 「どうせ上司評価が優先されるのだから、適当に記入してればいいや」
⇒ 「人事評価ってよくわからない・・・、面倒だしいいや」
【対応例】自己評価は、自分の仕事の点検であるとともに、役割を認識する機会でもあることを伝えることが必要です。
☆ 自己評価の意味を教える。(自己評価は自分の仕事の振り返る機会であること)
☆ 評価結果がどのように活用されるのか、その重要性を教える。
*~*~*~*~*~*
自己評価が高いスタッフの心理は、様々だと思いますが、
ある程度の傾向を掴んでおくことで、何らかの是正が可能となります。
単に「自己評価が高いですよ」というのでは、納得性がありません。
「何故、この評価結果になったのか」というところから、被評価者の考えを引き出すことから
始めることが大切なのです。
自己評価は、人材育成の原点?!(人事評価シリーズ16)
2018年09月23日
人事評価制度では、上司評価(他者評価)が賞与や昇給等の処遇に使われるため、
自己評価は軽視されがちなのですが、人材育成が目的であるならば、
自己評価がしっかりできる人材を育てることが大切だと思うのです。
そこで、そもそも「自己評価」とは何ができることなのかを考えてみます。
*~*~*~*~*~*
自己評価とは…
☆ 自分の得意・不得意を認める行為
☆ 求められる役割、行動に自分を照らし合わせる行為
の2つのことをすることだと思います。
要は、自分ができることとできないことを振り返ることと、組織の中での自分の役割に対して、
どこまで到達している状況なのかの自分点検作業です。
ここがしっかりできていれば、自己点検の結果、次に何をすべきかを自分で考える、
もしくは自分で考えられないのであれば、上司や周りに相談してみるという次の行動に移れるわけです。
とはいえ、自己評価が必ずしも正しいとは言い切れない子こともあります。
自分はよいと思っていても、周囲は「それは違うよ」という声を聴いてみることも必要です。
それが、上司評価(他者評価)です。
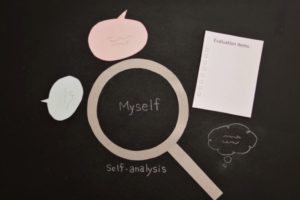
*~*~*~*~*~*
人事評価制度が嫌われる理由の一つに、
上司評価(他者評価)と自己評価が食い違ったときの嫌な気持ちになってしまうことがあります。
では、他者評価はどのように受け止めればいいのでしょうか。
まずは、冷静に受け止めてみることです。実は、他者評価のマイナスな評価は、
「自分が気付いていない自分」であり、より自分を高める材料となるはずなのです。
「へぇ~私ってそう見られることもあるんだな・・・」という受け止め方でいいのです。
自分を少し離れた場所から見るイメージです。
*~*~*~*~*~*
上司評価(他者評価)を活用しつつ、自己評価も正しく行える人材、組織にたくさんいてほしいですね。
さらに言うならば、自己評価が正しくできるとは、次のことができる人だと思います。
1.組織における自分の立場、役割を認識できている
2.立場、役割を踏まえ、自分がやるべき仕事を選択し、実践できる
3.実践するための知識や技術がある、もしくは習得しようと自分で努力している
4.実践した結果、できていることとできていないことを区分できる
5.4.の結果を踏まえ、次にやるべきことを選択し、行動する
自分の強みと弱みを受け止め、弱みをカバーするために何をすべきか、
強みを使って何ができたのかを踏まえ、次へのステップを考えらえる、
自分の高め方を知っている、自分の問題を自分で解決できる、
というのが正しい自己評価だと思うのです。
1.~5.までのことができるスタッフ、皆さんのチームにどのぐらいいらっしゃいますか?
人事評価制度において、自己評価は人材育成の原点だと思いませんか?
「社会に出ると必要だよ!」の納得度
2018年09月21日
先日、我が家のJK(女子高生)と大げんかをしました(~_~;)
けんかの原因は・・・
娘が進学のための願書を書き終え、封入して完了!だったのですが、
念のため、「宛名の”行”、”御中”に直した?」と確認したところ、「まだ」との返事。
「直してから送ってよ」と更に返すと、娘からこんな言い分が(-_-;)
「これが、合否に関係あるわけ? 成績と関係ないじゃん! 受験の内容じゃないじゃん!」
こちらは、「そういうもんなの!」とちょっとキレ気味に返してしまいました。
そこから、大げんか勃発です(@@;)
*~*~*~*~*~*
その後、冷静に考えてみました。
娘の言い分も確かに間違っているわけではありません。
本来、受験は高校の成績、当日の試験結果等がどうであるかの確認です。
封筒の書き方は受験科目ではありません。
そうすると、親として、何故、封筒の宛名を「行」から「御中」に修正するのかを
説明すべきだったと、反省しました(>_<)
*~*~*~*~*~*
このことは、言ってみれば日本的礼儀だけのことです。
送り先がこの日本的礼儀を重んじているかどうかはわかりません。
しかし、私たちはそのような中で育てられてきました。
娘の世代は、手紙を書く、手紙を送るという習慣は全くと言っていいほどありません。
それはメールやSNSに取って代わってしまっているからです。
「誰かに何か伝えたい」の願いを実現するには、手紙ではなく、メールやSNSなのです。
手紙の習慣をほとんど体験してこなかった娘世代にとって、「御中に修正する」ことは
全く理解できないことは言うまでもないことだと気づきました。

*~*~*~*~*~*
けんかが収束したとき、娘に改めて伝えました。
もし、受験生であなたと同じ点数の人がいたとき、どちらを合格させるかとなったら、
受験科目以外で常識がある生徒かを判断する材料になるかもしれないんだよと。
本来の受験科目ではありませんが、そういうこともしっかりしているんだということが
時として重要な要素になりうるということを話しました。
※~※~※~※~※~※
社会に出ると、幅広い世代の人たちと交流することになります。
それぞれの世代が大切にしてきたことを全く知らずに社会に出るのと、
一通りのことを少しは知っているとでは、おそらく交流のしやすさの点で
大きく違いが出てくると思うのです。
さて、我が家のJKはどこまでそれをわかってくれたのかな???
評価が厳しい人、甘い人(人事評価シリーズ15)
2018年09月17日
評価は、人の頭の中にあるものさしの付け合わせ作業です。
目に見えないだけに、客観的な基準などをたくさん用意して、
できるだけものさしのメモリ合わせをするわけですが、
それでも評価者と被評価者の食い違いは出てきてしまいます。
食い違いの原因の一つとして、評価者が仕事に対して、厳しめの人なのか、甘めの人なのかが
評価結果に反映されるということがあります。
では、厳しめと甘め、どちらのタイプなのかを振り返ってみませんか?
*~*~*~*~*~
◆◇◆ 評価の厳しさ甘さの傾向、事象~こんなことになっていませんか?~ ◆◇◆
👉厳しめの人
☑ スタッフのモチベーションが低い
☑ スタッフをほめることが少ない
☑ 日常から注意することが多い
☑ 全体的に評価表の評価結果が低すぎる(低い評価が部署全体の3~4分の1程度ある)
⇒ これは、評価結果が低い項目が多いということは、部署運営においてもミスが多かったり、
トラブルが多かったりと仕事全体が上手く進んでいないということですが、実際はどうでしょうか?

👉甘めの人
☑ やってはいけないことを明確に伝えられない
☑ スタッフに注意すべきときに注意できないことがある
☑ 評価結果のフィードバックで単刀直入にマイナス評価を伝えられていない
☑ 全体的に評価表の評価結果が高すぎる(高い評価が部署全体の3~4分の1程度ある)

⇒ 厳しめとは反対に、個々の評価結果がよいということは、部署全体もいい成果が出ているはずですが、
実際はどうでしょうか?
*~*~*~*~*~*
では、厳しめと甘めのそれぞれのタイプの評価者、部署運営にどのような影響が出ているのでしょうか。
◆◇◆ 厳しめと甘めの弊害 ◆◇◆
👉 厳しさの弊害
* 認められないことによる不平・不満が出る
* 指示待ち状態に陥る、指示されたことしかしない
* 常に張りつめた職場の雰囲気である
* 個々のマイナス面を指摘しあうようになる
👉 甘さの弊害
* 小さなミスが発生しやすい
* 自己判断をするスタッフが増え、仕事の進め方に支障が出る
* 職場の雰囲気はよいが、仕事のけじめがない(だらだら残業など)
* 個々のマイナス面をお互いで許しあってしまう
さて、評価者のみなさんはどちらのタイプでしょうか。
どちらのタイプというよりも、どちらよりの評価をしている傾向にありますか?
*~*~*~*~*~*
いずれにしても、弊害を防ぐためにも、対策が必要です。
次の対策によって、弊害を少しでもなくすることができると思われます。
〈対策①〉評価の基準を理解、把握しているか再度確認すること
⇒ 厳しめ、甘めともに、”自己基準”で評価している可能性が高いです。
所属する組織の基準を見返してみましょう。
〈対策②〉一つ一つの評価項目について、出来たことと出来ないことの両方を思い起こすこと
⇒ 厳しめ、甘めに偏りがちな人は、出来るか出来ないかの片方で考えがちです。
両方の側面でスタッフを観ることも必要です。
〈対策③〉他部署の評価者と評価結果の情報交換をすること
⇒ 客観的な視点を持つために他部署の同じ経験年数・ラダーのスタッフで評価結果を比較してみましょう。
迷ったら情報交換で、自分の評価基準が厳しいか甘いかの確認の機会を作ることです。
そろそろ30年度上期の評価時期になりました。
自分のタイプ、振り返ってみませんか?
行動・態度・意欲の評価の特徴と気をつけたいこと(人事評価シリーズ14)
2018年09月14日
評価項目のことは、人事評価シリーズ8の「評価項目は、組織の期待値でありモデル」であり、
以下のように述べました。
①与えられた仕事、役割が正しく実践できているか(「成績評価、業務成績評価」などと言われます)
⇒ 評価表の項目では、「仕事の質」、「仕事の量」、「役割の遂行度」など
②仕事をするときの態度や姿勢、意欲は一生懸命さが行動に表れているか(「行動評価、情意評価、勤務態度評価」などと言われます
⇒ 評価表の項目ではい、「規律性」、「責任感」、「積極性」、「協調性」など
③仕事をするときに必要な知識や技術、スキルが身についているか(「能力評価」などと言われます)
⇒ 評価表の項目では、「知識技術技能」、「理解力」、「伝達力」、「コミュニケーション力」、「情報処理力」など
①、②、③の3つの視点で、バランスよい人材を育成したいという期待値が込められているということでした。
人事評価は、できる限り客観的になるよう、評価者はその努力をする必要があることも述べました。
それでもなお、客観性が担保しにく評価があります。
それが、②の仕事をするときの態度や姿勢、意欲などの評価です。
*~*~*~*~*~*
態度や姿勢、意欲に関する評価は、次のことが評価内容で設定されている組織が多いと思います。
👉 社会人として、職業人として、組織の一員として、望ましい姿が示されている
👉 就業規則その他諸規則、仕事の基本に基づいた基準が示されている
👉 よりよい仕事の成果を導くためのプロセスが示されている
(例えば、「報告、連絡、相談をタイミングよく行えていたか」など)
👉 年一度もしくは半年に一度、自らの態度や姿勢、意欲を振り返るチェックリストとして活用できる
このように、態度や姿勢、意欲に関する評価は、私たちが組織で仕事をする上で、
新人でもベテランでも管理職でも、誰もが気をつけるべきことが示されています。
とても大切な評価であることが理解できると思います。
*~*~*~*~*~*
大切な評価ではありますが、次のような特徴があるため、
評価するときに気をつけてほしいことがあります。
👉 具体的な行動・態度を見ていなければ、評価結果を導き出せない
どんな態度だったのか、どんな意欲がみられたのかは、仕事ぶりを観察していないと
評価結果は出せません。評価するためには、行動の事実が必要であることは以前に述べました。
👉 対象とするものが行動や姿勢であるため、明確な結果が見えにくい
仕事の成果は、結果がでますし、必ず終わりがありますから、
ある程度明確にできた、できていないの判断がしやすいのですが、
態度や姿勢、意欲は終わりがありませんので、結果を捉えにくいという特徴があります。
👉 人によって(評価者、被評価者含め)、基準の捉え方に誤差が生じやすい
態度や姿勢、意欲は、人によって、大事にしているポイントが異なります。
要は「一生懸命に仕事をしている」の「一生懸命」は、それぞれの仕事への向き合い方になります。
そうなると、それぞれの尺度が異なるため、評価者と被評価者の一致点を見つけにくいという特徴があります。
例えば、規則を厳密に守ることをよしとする人と、規則はある程度曖昧でも、仕事の効率が大事という人もいます。
明らかに尺度が異なるため、評価結果が折り合わないことがあるわけです。
👉 評価結果を被評価者が信頼しにくい
仕事への向き合い方のポイントが異なれば異なるほど、被評価者は評価者の結果に対して、
疑問を抱く度合いが高まり、評価結果を信頼しにくくなります。

*~*~*~*~*~*
では、上記のことをどう回避すればよいのでしょうか。
次の対策を参考にしてみてください。
【対策①】
評価結果は、根拠あるものにすること
👉 根拠(具体的行動の事実)をスタッフに説明をできるようにすること
👉 スタッフとの面接のたびに、着眼点の捉え方の誤差を修正しあうこと
👉 評価者同士の着眼点の捉え方を定期的にすり合わせること
👉 評価するのにに迷ったら、周囲の評価者に相談してみること
👉 日頃からスタッフとの信頼関係を築く努力をすること(←やはりこれが一番ですね!)
*~*~*~*~*~*
態度や姿勢、意欲はいいに超したことはありません。
意欲があって、初めて充実した成果が生まれてきます。
大切な評価項目ですので、しっかりした評価、信頼される評価を導き出せるよう評価者も努力したいものですね。
評価は、仕事の「点検」です(人事評価シリーズ13)
2018年09月09日
「評価」というと、良いor悪い、できるorできないなど、優劣を判定する意味で使われます。
ですので、人事評価は、評価者から「あなたは出来る人、出来ない人」と判定される感じがするため、
毛嫌いされる要素があるのです。
しかし、共に仕事をするのに、判定することは全く意味のないことです。
元々は、人事評価をすることで、組織内の仕事が上手く進むことを目的としているわけですから、
人事評価の「評価をする」本来の意味を理解することは大切なことだと思います。
そこで、評価者の役割から「評価をする」本来の意味を考えてみましょう。
「評価」を「点検」ということばに置き換えてみると、
本来の意味を理解しやすいのではないかと思います。

*~*~*~*~*~*
評価者の役割には次の5つの役割があります。
① 仕事の点検する役割
👉 業務遂行管理ですね
② 点検して修正する役割
👉 スタッフの業務指導、アドバイス、サポートの役割ですね
③ スタッフのできている状態、できていない状態を見て、仕事を割り当てる役割
👉 業務ローテーション、組織目標(病院目標、部署目標)の割り当ての役割と言えるでしょう
④ スタッフの得意なことを知り、それを伸ばす(活用・・・使う)役割
👉 スタッフの能力開発、新たな業務の経験の機会を与える、目標設定のサポートなどの役割ですね
⑤ スタッフの不得意なことを知り、それをカバーする役割
👉 スタッフの業務遂行の見守り、サポート、指導アドバイス等、リスク管理に相当する役割ですね
*~*~*~*~*~*
5つの役割、よくよく見ると管理職の役割の一部に相当すると思いませんか?
要は、「評価をする」こと=管理者としての役割遂行なのです。
いかがですか? 「評価」ではなく「点検」と置き換えて、人事評価に向き合ってみませんか?
評価段階の評語は、できるだけ平易なことばで(人事評価シリーズ12)
2018年09月06日
評価基準は、次のことについて設定する必要があることは、前回(人事評価シリーズ11)で
お伝えしました。
(人事評価シリーズ11から引用)
①何段階にする?
3段階、4段階、5段階など、段階の数を設定
②設定した段階の評語の表現はどうする?
ⅰ)数字(5・4・3・2・1)で表現、アルファベットで表現(S・A・B・C・D)など
ⅱ)各段階の基準(例:「5」は、「期待をはるかに上回る」など)
*~*~*~*~*
今回は、②設定した段階の評語の表現についてお伝えします。
ⅰ)数字で表現?アルファベットで表現?
👉どちらでもいいと思いますが、従業員の皆さんが「しっくり」くる、「使いやすい」と思う方でよいですね。
ⅱ)各段階の基準の表現は?
👉この評語の表現は、大変重要です。部下と上司の評価のすり合わせの基準になるものです。
5段階評価での一般的な評語の表現は、次のとおりですが・・・
S :期待をはるかに上回る結果が得られた。
A :期待を上回る結果が得られた。
B :期待どおりの結果が得られた。
C :期待をやや下回る結果となった。
D :結果をはるかに下回る結果となった。
ただ、これだけの基準ですと、部下と上司との評価の食い違いの振れ幅が大きくなる可能性があります。
これ以外に、双方の評価結果に食い違いが出ないよう、別の表現も付け加えておくとよいでしょう。

*~*~*~*~*
例えば・・・このような表現もあります。
ポイントは、できるだけ「平易なことば」で表現することです。
S評価:
・まれにみる優秀さである ・誰からみても模範的である ・非のうちどころがない
A評価:
・日常は全く問題がない ・先駆けて自ら動く ・言われなくても動く
・リスクを考えて先手が打てる
B評価:
・手がかからない ・時々質問をしてくるものの、その後は問題がない
・教えれば、ひととおり出来る ・可もなく不可もない状態
C評価:
・指導したら、かろうじて出来る状態 ・時々、見守りや確認が必要
・自立までに時間がかかる ・多少、手がかかる
D評価:
・何度指導しても、任せられない ・ミスが多く、手がかかる
・部署、チームに支障をきたしている
その他、「%」で表現する方法もありますね。S評価は、90~100%のように。
*~*~*~*~*
いずれにしても、この評語が評価のすり合わせの原点になります。
できるだけ多くのスタッフの評価結果の振れ幅が拡がらないように表現の工夫は必要だと思います。
評語の表現は、人事担当者が単独で決めるのではなく、
現場の複数のメンバーからの意見を取り入れながら決めることをお勧めします。